この4月から、息子は小学校3年生、娘は小学校1年生になりました。
我が家では引き続き通塾なしの家庭学習です。
基本放課後は毎日公園に遊びに行っているので、1日あたりの勉強量はさほど多くありませんが、一応毎日家庭学習をしています。
2人とも通信のZ会と市販ドリルをやっているのですが、どのドリルを何ページくらいやるかという管理を我が家では「スタディプランナー」というノートを使って行なっています。

(我が家ではピンクが小1娘用、ライトグリーンが小3息子用です。)
スタディープランナーは様々な種類がありますが、我が家ではコクヨのスタディープランナー、デイリータイプのB5サイズを使っています。
Contents
我が家のスタディプランナー活用法
私がプランを書き、子どもたちができた項目にチェックを入れています。
書くのは毎晩の丸付けタイム。(疲れてどうしても夜にできないときは朝一でやります。)
子どもたちの学校からの帰宅時間や習い事の有無を考慮し、日によって学習量を調整しています。
・ていねいに書こう
・問題をよく読もう
・テスト頑張ろう
etc.
・ちょっとした復習問題。(例えば最近辞書で調べていた言葉の意味を問う問題などを書く。)
・よくできていたところを褒める
・注意してほしいことを書く
etc.
スタディプランナーを使うことによるメリット
その日やる勉強を見える化できる
子どもたちはその日何を勉強すればよいかノートを見ればわかるし、
親は丸付けの際ノートを見れば子どもたちがその日何をやったのかわかります。
やり忘れがなくなる
チェック欄があるので、子どもたちがやった項目にチェックを入れていくことでやり忘れがなくなります。
以前は
母「今日音読やってないけどないの?」
息子「あ!ある!忘れてた!」
という会話がしょっちゅうありましたが、今はなくなりました。
達成感を味わうことができる
先日スタディプランナーの1冊目をやり終えたのですが、振り返ったときにかなりの達成感を味わうことができました。
何事も長続きしない私が毎日欠かさずスタディプランナーの記入をし、子どもたちもスタディプランナーに書かれた学習に毎日取り組むことができました。
スタディプランナーを使うことによるデメリット
めんどくさい
とにかく書くのが面倒です。
(私がめんどくさがりだからかもしれません…。)
この作業を面倒だと感じない人であれば特にデメリットはないかもしれないですね。
綺麗に見やすくする書くための工夫
見た目が綺麗で見やすいほうが子どもたちのやる気もupするかな、と思い、綺麗に見やすく書くように心がけています。
そのために使っているアイテムが、フリクションボールペンとマイルドライナー。
まとめ
スタディプランナーでの学習管理、我が家では順調なのでこれからも続けていきたいと思います。
いずれ自分たちですべて書いて管理できるようになるかな?
スタディプランナーはデイリー、ウィークリーのものがあったり、いろいろなメーカーから発売されています。
100均のものもあるようなのでぜひ使いやすそうなものを見つけてくださいね。
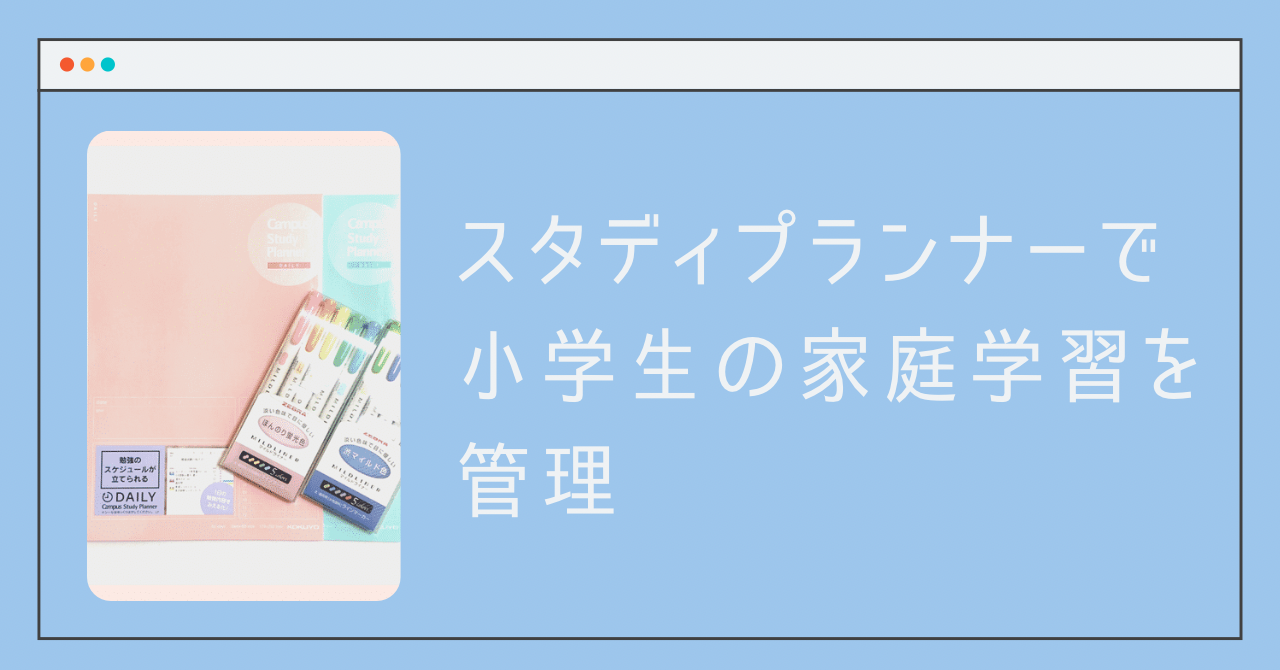


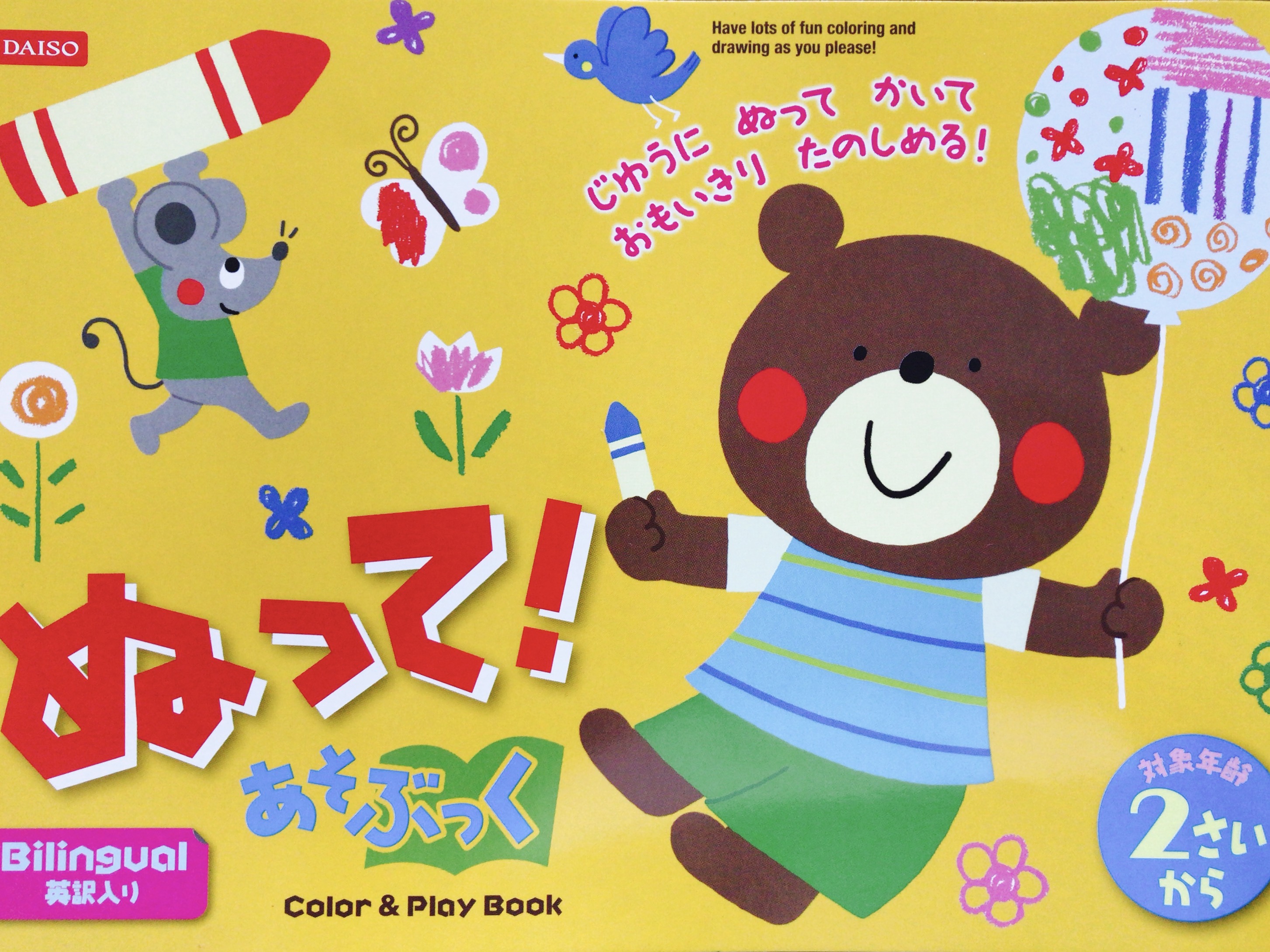
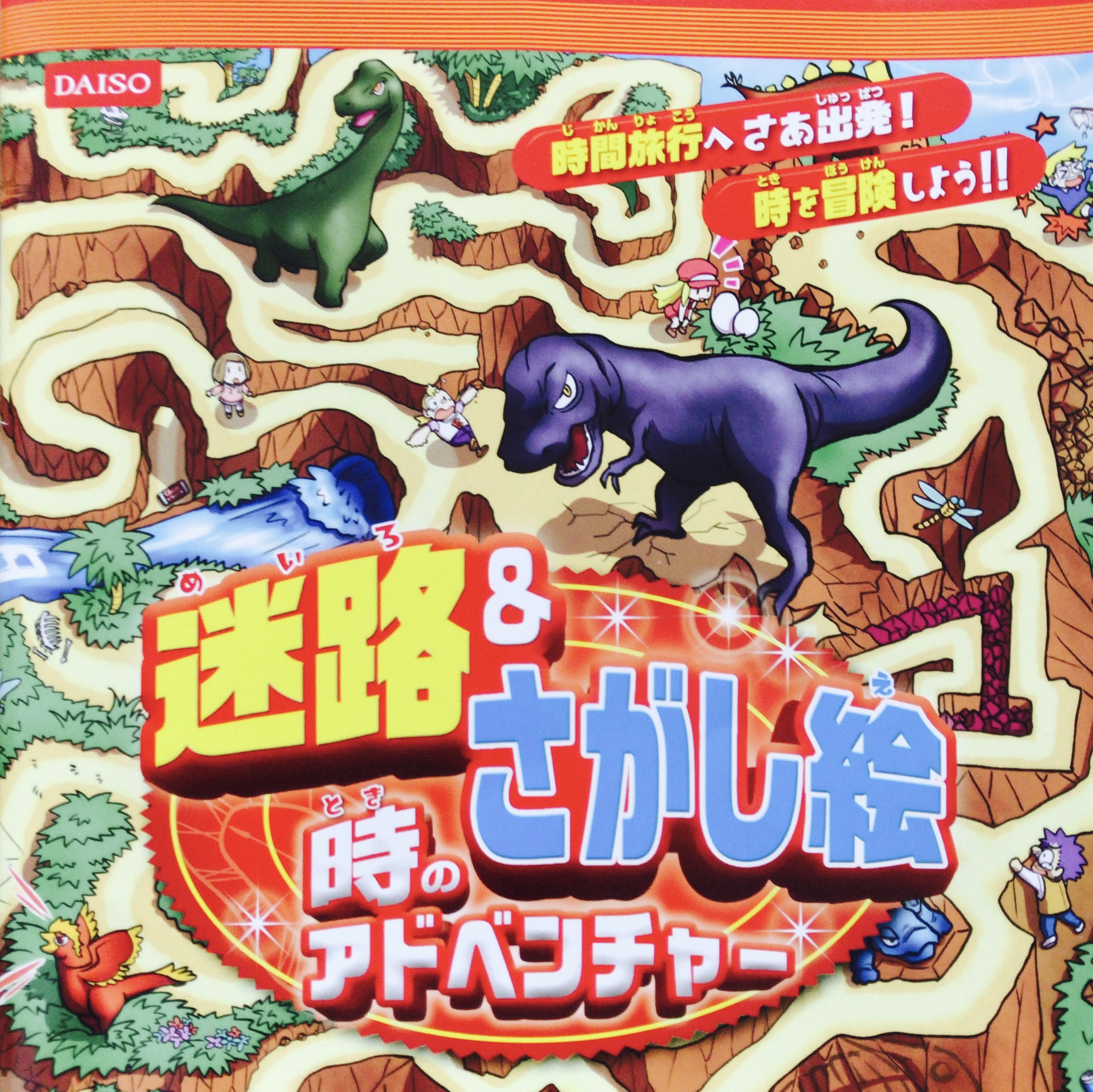

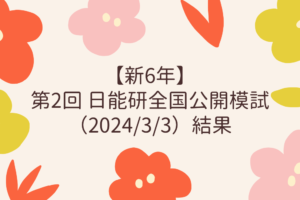

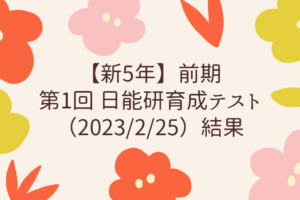
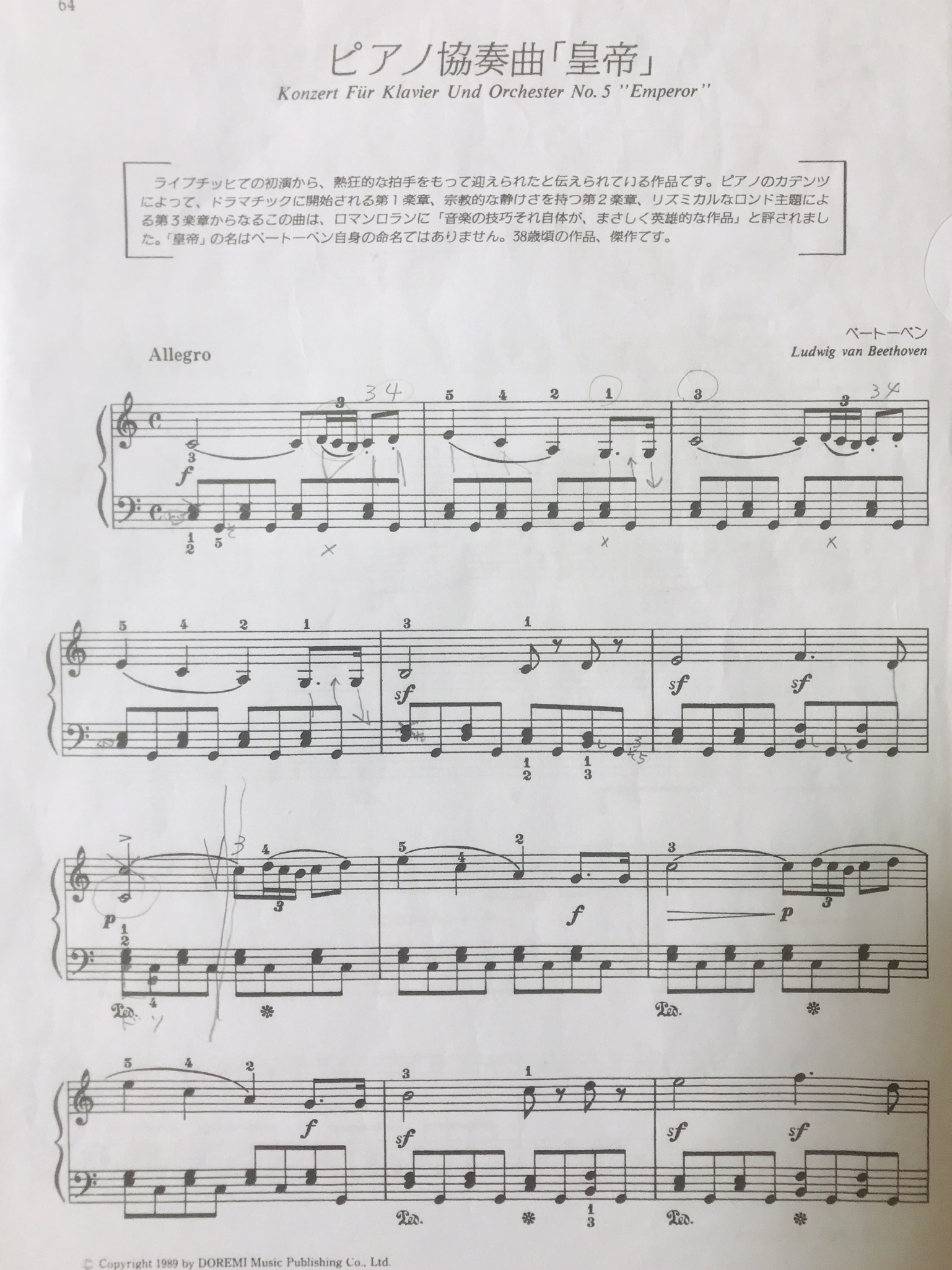
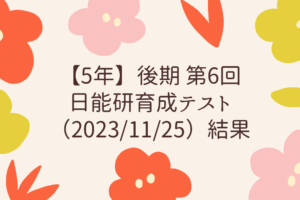

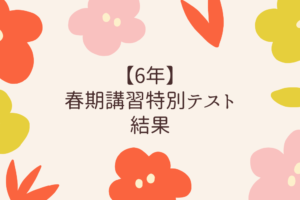
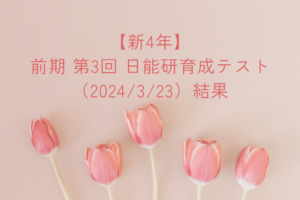
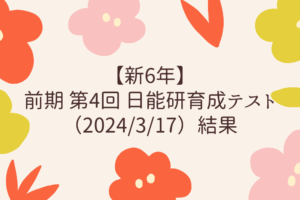

コメントを残す